将来性に富んだ画期的なソリューションが登場した2022年の「協創の祭典」
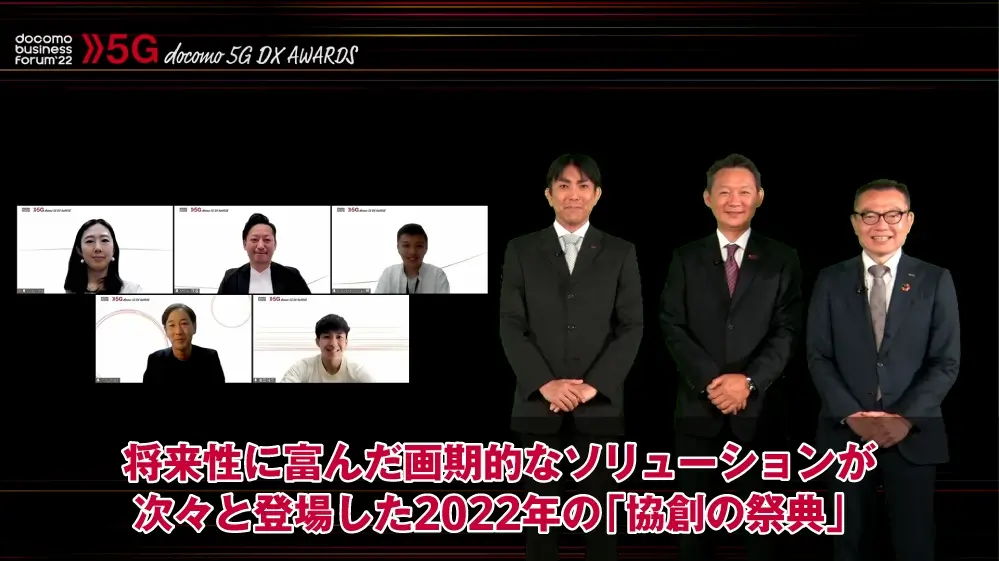
5Gの新たな協創ソリューションの創出を目指すNTTコミュニケーションズとNTTドコモ・ベンチャーズ。第3回目となる「docomo 5G DX AWARDS® 2022」を開催し、5Gとのシナジーに優れたアセットの発掘・活用に取り組んだ。
過去のアワードから5つの協創ソリューションが誕生
2022年10月20日、NTTコミュニケーションズのイベント「docomo business Forum'22」において、NTTコミュニケーションズとNTTドコモ・ベンチャーズ共催の「docomo 5G DX AWARDS 2022 表彰式/プレゼンテーション」がオンラインで開催された。第3回目となる今回は、建設・メディア・小売り・医療など「8つの業界+SDGs」をテーマに、5Gと親和性のあるアセットを募集。最終選考会を経て各賞を受賞した、将来性や魅力にあふれるアセットを見ていこう。
主催者でプレゼンターの1人でもあるNTTコミュニケーションズ 執行役員 プラットフォームサービス本部 5G & IoTサービス部長の藤間良樹氏は冒頭に、2018年2月に開始した「ドコモ5Gオープンパートナープログラム🄬」のパートナー数が「5300社」を超えたことに加えて、昨年のアワードから最優秀賞を獲得したDataMeshの「DataMesh Director」や優秀賞・SAJ-DX特別賞だったサイエンスアーツの「Buddycom」など、「5つの協創ソリューションが誕生した」ことを報告。さらに、新ドコモグループの新たな法人事業ブランド「ドコモビジネス」として、「今後もパートナー企業とともに、先進技術の創出や実装に一層取り組んでいく」と語った。
ここからは、各受賞アセットのプレゼン内容とともに、受賞における評価のポイントや受賞企業のコメントを見ていく。さらに、選考に携わったプレゼンターのコメントも紹介していく。
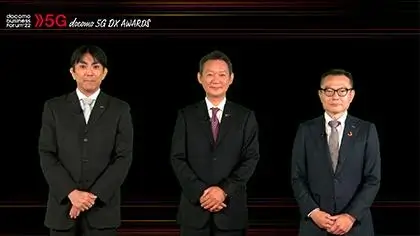
実際の導入も進むリアリティにあふれたソリューションが続々登場
●株式会社MOYAI
栄えある最優秀賞に輝いたのは、LED蛍光灯一体型多機能ネットワークカメラ「IoTube」を展開するMOYAI。IoTubeは、「鉄道車両への防犯カメラの設置」や「AIの社会実装への障害」といった社会課題に注目し、それらを解決する新たなイノベーションとして開発された。
IoTやAI、クラウド、通信技術を組み合わせたIoTubeは、チューブ型のLED蛍光灯に通信機能付きのカメラを組み合わせたデバイス。さまざまなセンサーやマイクなども内蔵し、エッジAI機能にも対応する。これにより、危険の発見や省人化などに、幅広い用途に活用できる。さらに、クラウド型のWeb UIソリューション「THEASIGHT」を用意することで、利用者のユーザビリティを向上させている。
すでに京王電鉄での導入が進んでおり、すべての車両への取り付けを推進中。リアルタイムストリーミングや双方向通話、過去動画取得などの機能を搭載することから、鉄道会社の司令部が車内の様子をリアルに確認してサポートすることが可能になっている。さらに、エッジAIによる乗降客や音声の解析にも対応し、with コロナ対策やエキナカ開発、非常通報音の検知など、さらなる利便性の向上にも寄与することが可能だ。また将来的には、スーパーやコンビニでの店内メディア価値を高める取り組み、オフィスや学校でのメンタルヘルスケア、振り込み詐欺などの被害防止、農業支援AI技術の導入などへの展開も視野に入れる。

藤間氏は、受賞のポイントとして「非常事態を迅速に検知できるなど、いままさに起こっている社会問題の解決に大きく貢献できる」という点を挙げた。さらに、このソリューションはすでに京王電鉄に導入されていることから「その価値がすでに認められている点も評価した」と補足した。MOYAI 代表取締役CEOの渡邊亮氏は「事業の運営においてはさまざまな悩みなどがあるなかで、今回のような形で認められたことは励みとなる。今後はNTTコミュニケーションズの実装力なども借りながら、さらなる社会課題の解決に向けて邁進していく」と力強く語った。
●Pudu Robotics Japan株式会社
優秀賞は、中国・深センに本社を構えるPudu Robotics Japanが受賞した。Pudu Robotics Japanではこれまでに飲食店向けの配膳ロボットを展開してきたが、今回は業務用清掃ロボット「PUDU CC1」を紹介した。
PUDU CC1は、1台に「スイープ」「床洗浄」「吸引」「乾拭き」という4つの機能を搭載し、あらゆる清掃ニーズに対応する。モジュラーコンポーネント設計により、手間のかかる付属品の着脱も、簡単に行えるようになっている。さらに、大理石や床タイルなどの硬い床からローパイルカーペットなどの柔らかい床まで、各床材で利用できる。
また、専用ワークステーションを用意し、ワークステーションでの自動給排水が可能。電力が低下すると、ロボットが充電スタンドへ自動的に帰還する機能も備える。そのほか、複数ロボットでの共同作業を実現するマルチマシン連携運用や自動交換、マルチマシン・ツー・マルチワークステーションなどの機能も用意し、幅広い施設での運用が可能。清掃のデジタル化にも対応し、スマホアプリを使ったリモート操作や清掃実績のリアルタイム通知、清掃レポートの自動生成などにも対応する。

加納氏は受賞のポイントとして、「人とロボットの協働によって現場の課題を解決する可能性と、ロボット活用における実用性を評価した」とし、「新しいワークスタイルデザインにつながるはず」と付け加えた。Pudu Robotics Japan 営業のLeo Huang氏は「今後もより良いロボットを開発を継続し、新しいソリューションの実現や社会への貢献を目指す」と語った。
●株式会社フォーラムエイト
本アワードに協力団体として参画するソフトウェア協会(SAJ)のSAJ-DX特別賞はフォーラムエイトが獲得。Webブラウザのみで利用できるクラウド型で、アバターを介したコミュニケーション機能なども備える3DVRプラットフォーム「F8VPS」を紹介した。
F8VPSの最大の特徴は、さまざまなサービスやシステムなどとの柔軟なAPI連携に対応している点にある。例えば、テレワーク環境やイベント・展示会、観光、教育、商品PRなど、分野を問わず最小限のコストで実現できる。さらに、基本機能として利用者は3D空間を任意で構築することが可能。オーサリング機能も充実しており、作成した3D空間のレイアウト共有や、待機室・会議室・プレゼンルームといった別領域の設定などにも対応する。
現在はB to Bでの活用に注力しており、例えば企業のバーチャルオフィスや建設現場・工場でのデジタルツイン環境としても活用されている。また、近年は日本と海外の学校での同時授業やGIGAスクール構想などの研究開発、あるいは自動運転のモニタリングや建設機器の遠隔操作などにも活用されており、高速・大容量、低遅延を強みとする5G通信との親和性も高い。

高村氏は、受賞のポイントとして「VRやメタバース、デジタルツインなどの最先端技術を活用するとともに、APIによってそれらを柔軟に連携することが可能。さらに、5Gの特徴である高速・大容量通信の利点を活かしたソリューションとしてDXを支援している」と評価。フォーラムエイト 執行役員 営業サポート管理マネージャの新田純子氏は「5Gの特性が必要不可欠であるF8VPSによって、さまざまな企業のDX推進をサポートしていく。そのためにも今後、NTTコミュニケーションズやSAJと共に発展していきたい」との抱負を述べた。
●株式会社PoliPoli
今年度の募集テーマの1つである「SDGs」に最もふさわしいアセットを表彰する「SDGs特別賞」に輝いたのはPoliPoli。住民などからの多様な意見をオンラインで募集するプラットフォーム「PoliPoli Gov」で、行政の政策推進を支援している。
PoliPoli Govでは、わかりやすい政策発信と建設的なコミュニティ運営により、住民の声を集めることに特化したプラットフォームを運営。そこからマーケティングや広報、政策共創につなげることで、ソリューション展開を進めている。具体的には、住民から意見を募るとともにフィルタリングすることで有効な意見を抽出するほか、意見の募集期間でマーケティングや広報などのファシリテーションを行い、コミュニティのさらなるマネジメントにつなげいている形だ。
さらに、「どのような内容を発信すべきか」や「どんな問いを立てるべきか」など、あらゆることをマネジメントし、行政担当者が簡単に住民などを巻き込めるような提案ができる点も強みの1つ。また、すでにNTTコミュニケーションズと連携し、宮城県での取り組みも始まっており、住民をより巻き込んだ政策共創の実現や住民の課題を解決するDXなどに挑んでいる。
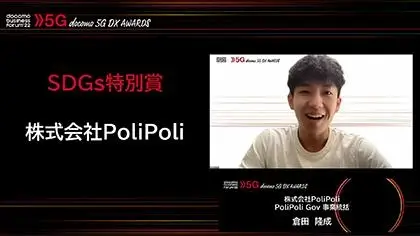
加納氏は、受賞のポイントとして「持続可能な社会を目指して住民の意見を聞くための広報やマネージメントをサポートするなど、その実績とユニークさが評価された」と説明した。PoliPoli PoliPoli Gov事業統括の倉田隆成氏は「NTTコミュニケーションズとは、地方自治体との連携を一緒に強めていきたいと考えている。それだけに、今回の受賞は大変嬉しく名誉なことだ」と喜びを示した。
●株式会社mint
XRなどの重要技術と5Gとのシナジーを見据えた「ウェアラブルデバイス特別賞」は、mintが受賞した。mintでは現在、外国人観光客を対象とするサイクリングガイドツアー「sokoiko!」を運営していることから、今回はそのツアーでスマートグラスを活用してユニバーサルツーリズムを実現する「ひろしまサイクリングsokoiko!×スマートグラス『VUZIX M400』」を披露した。
そもそも、sokoiko!ではこれまで、「同じ日に同じタイミングで異なる言語のガイドができない」という課題があった。このような「言葉の壁」の問題に対し、その壁を超えていく方法として考案したのが、ガイドの内容を「スマートグラスに翻訳字幕で表示する」という今回の仕組みである。これにより、言語の異なる外国人観光客を同時に案内できるようになるほか、聴覚障がい者がツアーに参加することも可能になると考える。
これに加えて、スマートグラスに搭載されているカメラを利用し、日本にいない人でもオンラインでツアーを楽しめるサービスにも対応。例えば、ツアーの参加者とともに、母国にいる家族もオンラインで一緒にツアー体験ができるようになることから、「距離の壁」も超えることが可能になっているという点もポイントとなる。

藤間氏は、受賞のポイントについて「スマートグラスを介して言葉や距離の壁を取り払っている」という点に注目。さらに。「ユニバーサルなサービスやプロダクトが求められる昨今の状況にもマッチしている」と評価した。mint 代表取締役社長の石飛聡司氏は、今回の受賞で「これまでの地道な努力が実るとともに、新しい可能性が広がった。他分野への発展なども見据えて、今後もより一層励んでいく」と笑顔を見せた。
若手の活躍や新たな領域への進出に将来性を感じた
イベントを終えてNTTコミュニケーションズの藤間氏は、今回の受賞者に若い人が多かったことや、アイデアの事業領域が行政などにまで広がっていた点に着目。実績のある企業の画期的なソリューションはもちろん魅力的だが、柔らかい発想や速いスピード感でチャレンジしていく若いスタートアップの姿勢には「非常に将来性を感じた」と総括した。さらに、そこから生まれた新しいソリューションを単に売って終わるのではなく、行政などと一緒に継続して取り組んでいくという考え方は「とても興味深かった」と振り返った。

ソフトウェア協会の高村氏は総括として、言葉としては広まりつつあるものの、その具体的な内容まではなかなか理解が及んでいないと思われる「DX」や「メタバース」、「デジタルツイン」といったキーワードが、今回紹介されたソリューションやサービスの中に「ちゃんとした形で組み込まれていた」という点を指摘。これは「5G」も然りだが、それらの中身や特性、強みなどを「しっかりと理解したうえで、しかも新しいビジネスとして構築されている」ことを高く評価した。もちろん、こういった動きはまだまだ始まったばかりだが、「今回のような機会がこれからもっと増えることを願う」として、さらなる発展に期待を寄せた。

一方、NTTドコモ・ベンチャーズの加納氏はまず、今回受賞した各ソリューションがこれまで後回しにされてきた「市民や現場の課題解決」にまで目を向けつつあることに注目した。そのような“手触り感のあるプロダクト”の台頭には前提として“5Gの土台”が必要となることから、そのすそ野の広がりに「5G時代の本格化」を実感するとともに、すべてのソリューションで「テクノロジーの進歩と急速な実用域への到達」を感じたそうだ。
さらに、スタートアップが本格的に個別課題の解決を狙うチャンスが来ている点にも触れ、大企業や中小企業、スタートアップがそれぞれの垣根を越えた「幅広いコラボレーションによって早期実用化を目指す世界が、いよいよ到来しつつある」と補足。広がりを見せる多彩な協創の機会を「今後もさらに生み出していきたい」と意欲を見せた。

5Gの商用サービスがスタートしてから早2年半が経過し、5Gは当たり前のものとなりつつある。そういった状況にあって今回は、5G時代の新たなユースケースとなるようなさまざまな協創の可能性を見ることができた。ドコモ5Gオープンパートナープログラムの協創がもたらす新たなソリューションの登場に、今後も期待したい。
※「docomo 5G DX AWARDS」「ドコモ5Gオープンパートナープログラム」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。