福岡と京都、個性派スタートアップシティに宿る歴史と文化
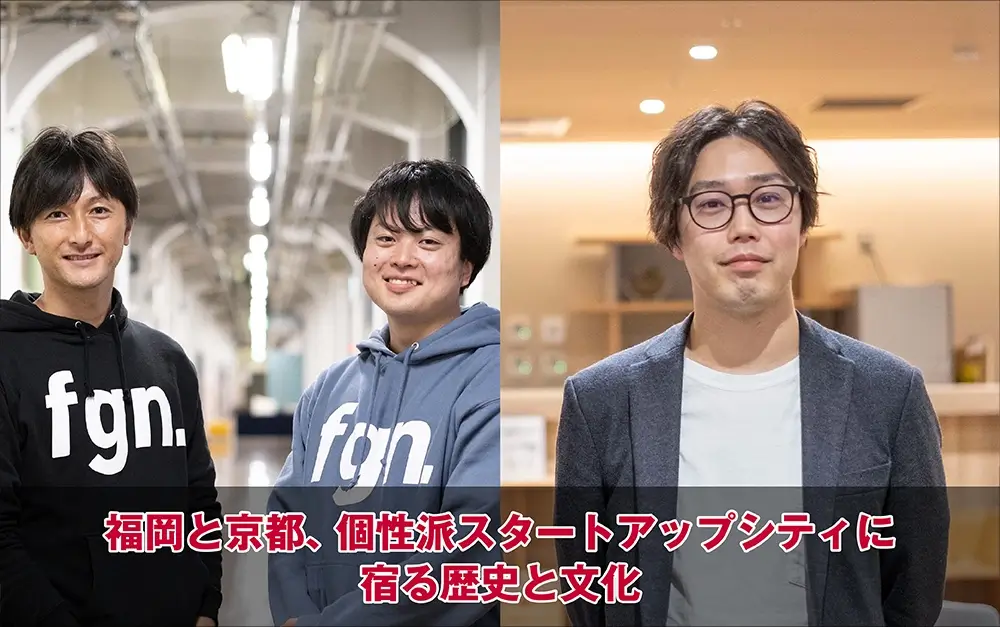
国を挙げて全国各地でスタートアップ・アコシステム形成が進む中、”世界への窓口”に認定されたグローバル拠点としは何を思うのか。いち早くスタートアップ支援を推進してきた福岡市、以前から独自の企業文化が根付く京都市にフォーカスし、地域発スタートアップの現状を聞いた。
日本中で芽吹き始めたスタートアップの種
現在、内閣府、経済産業省、文部科学省などが連携して「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」が進んでいる。
本戦略では、コンソーシアム形式によって大都市圏の各都市を4カ所のグローバル拠点都市に定めた。
「スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアム」‐東京都、川崎市、横浜市、和光市、つくば市、茨城県など
「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」‐愛知県、名古屋市、浜松市など
「大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム」‐大阪市、京都市、神戸市など
「福岡スタートアップ・コンソーシアム」‐福岡市など
NTTドコモ・ベンチャーズ(以下、NDV)もこの流れを踏まえ、各拠点とのリレーションを通じて将来有望なスタートアップの発掘や成長支援などに力を入れている。2021年には立て続けにグローバル拠点都市とのオンラインピッチイベントを開催し、現地の熱い盛り上がりを伝えてきた。そこからは、コロナ禍の逆風にも負けず、日本中で新たなビジネスの種が芽吹き始めている事実がたしかに感じられた。
今回は、グローバル拠点都市から福岡市と京都市にスポットを当てた。それぞれのキャラクターの違いは以下の内容に詳しいが、どちらも“街の勢い”を反映して伸び盛りである点は共通する。まずは福岡市の取り組みから紹介しよう。
福岡の背景にある「サービス業の強さ」
福岡市は、2010年代を通じて躍進した街の代表格だ。人口増加率は全国の政令指定都市でトップを維持し、2021年11月には162万人を突破した。人が集まれば、カネもモノも情報も集まるのは自然の摂理である。エネルギッシュな成長を糧に、福岡市では早い段階からスタートアップ支援に注力してきた。
2012年9月に「スタートアップ都市ふくおか宣言」を表明したことを機に、起業しやすい街のムーブメント醸成に着手。続く2014年5月には国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、あらゆる起業相談に応じる「スタートアップカフェ」や、地場企業とのビジネスマッチングイベント「FUKUOKA STARTUP SELECTION」などを通じて裾野の拡大を図ってきた。

地盤を築いた後、スタートアップが一元的に集まる“場”として2017年4月に「Fukuoka Growth Next」(以下、FGN)がオープンした。福岡市の中心に位置する旧大名小学校をリノベーションした施設で、これまでに522社・団体(2021年11月までの累計)が入居。2017年4月〜2021年11月における入居企業の資金調達額実績は64社・230億円を誇るなど、国内でも屈指のスタートアップ支援施設として名を馳せる。
市職員の立場からスタートアップ育成に携わる福岡市 経済観光文化局 創業支援課の清見康平氏は「市内に分散していたインキュベーション施設やスタートアップカフェを集約したいとの思いから、街のど真ん中でハブになる施設を探していた。FGNができたことで、スタートアップ支援がさらに加速した」と話す。

この言葉にあるように、街のど真ん中にあることがポイントだ。すぐそばに九州一の繁華街・天神エリアがあり、街の内外からのアクセスも良い。閉じられたインキュベーション施設の雰囲気は微塵もなく、いろんな人が行き交いながらコミュニケーションを深めている。抜群の周辺環境もさることながら、FGNが用意する充実の育成メニューもこれまでの実績に寄与。Fukuoka Growth Next 運営委員会事務局 事務局員 崎山勇気氏は、その内容を次のように話す。
「FGNでは、起業家向けに実践的な教育を行なうジャンプスタートプログラム、起業家のパートナーとなるデザイナーやエンジニア、PR人材の育成プロジェクト、国内外のベンチャーキャピタル(以下、VC)や大企業とマッチングの機会があるアクセラレーションプログラムなどを用意している。その結果が、数多くの大企業との協業や資金調達に結びついた。

これに加え、入居者の露出機会を増やすため定期的に『Growth Pitch』を開催。さらに米シアトルの『Founders Live』と連携した英語によるショートピッチの『Founders Live FUKUOKA』を開始し、海外マーケットに挑戦したいスタートアップも支援している」(崎山氏)
Founders Liveとの連携はアジアで初となる。清見氏は「我々のミッションは、福岡発の世界的企業を生み出すこと。Founders Liveはそのための施策の1つ。福岡のスタートアップには、世界を変えるような事業に取り組んでほしい」と言う。
全方位型のサポートは、入居者たちをたくましくする。最近の事例では、アプリで食事をごちそうする「ごちめし」を提供するGigiが急成長した。コロナが襲った2020年には、飲食店応援プロジェクトの「さきめし」が話題を呼んだことも記憶に新しい。スマートロックを使った空間シェアサービスを手がけるtsumugはテレワークのニーズを迅速にキャッチアップし、空室を活用した専有マイクロオフィスのサービスを始めた。
「コロナになって価値観や生活様式も大幅に変わったが、これらの企業はコロナだからこそ伸びていく市場に着目した。我々がアドバイスすることもあるが、自ら考えて突き進んでいる。その姿勢に頼もしさを感じる」と清見氏。崎山氏も「むしろ距離の制約がなくなり、海外のエンジニアと一緒に仕事をするケースなども増えた。FGNという場所の一体感を活かしつつ、スムーズに切り替えていた」と振り返る。
では、福岡ならではの特徴とは一体何か。清見氏は「福岡市は一級河川がないこともあり、製造業が盛んではない土地柄。そのため産業構造の約9割がサービス産業という地域特性があり、情報サービス系のスタートアップが多い」と指摘する。ソフトウェアやAIなどの知識創造型企業が発展しやすいのは、こうした背景があるためだ。
また、良い意味でのコンパクトさも特徴の1つ。FGNには起業家やエンジニアが集う「awabar fukuoka」があり、公式な紹介に限らず、フランクな交流からどんどん人的ネットワークが広がるのだという。「屋台文化が影響しているのか、人とつながるスピードが速い。FGNを卒業した先輩起業家が、新たにFGNに入居したスタートアップを外部メンバーとして助けるケースもたくさん見られる」(崎山氏)。

FGNを舞台に5G関連の新規事業創出ピッチなどを開催してきたNDVも、福岡のパワーに期待を寄せる。NDVの十川良昭氏は「福岡のスタートアップは理詰めで勝負するのではなく、どうすれば顧客の役に立てるのかを肌で感じ取っている雰囲気がある。面白く、温かく、それでいて新しい印象だ」と述べた。
同じくNDVの加納出亜氏は「福岡の魅力は何と言っても多様性。“こんなサービスが出てきたか!”というワクワク感を楽しませてもらっている。これまでのジャンル分けで判断できないユニークさを育む土壌がある」と分析する。

いずれにせよ、福岡が地域スタートアップ活性化の立役者であったことは揺るぎない事実だ。清見氏は「福岡市がスタートアップ支援に注力する最大の理由は、地方都市が頑張らないと日本経済が元気にならないから。その動きが全国に伝播して各都市が力を入れるようになってきたことは嬉しい」と語る。
だがそれは、都市間の競争が激化してきたことを物語る。「先ほど話したように、福岡市の弱点は工場がないこと。スタートアップ都市推進協議会で都市間の連携を行なっているように、例えば製造業に強みを持つ浜松市や、研究開発が得意なつくば市などと連携してお互いの都市の良さを組み合わせれば、相乗効果が生まれるに違いない。知恵を出し合いながら、最善の策を考えていかなければならない」(清見氏)。

これを受け十川氏は「全国の地域スタートアップのハブとなることこそNDVの役目。お互いに技術やアイデアを補完しあえる場を提供することで、次につながる何かが生まれるはずだ」と意欲を見せた。全国都市間での技術・アイデア交流、あるいは企業同士のマッチングは、2020年代を生きるスタートアップにとって不可欠の要素になるかもしれない。
起業の都はライフサイエンスとハードウエアが武器
悠久の歴史を持つ京都。世界に誇る観光都市である一方で、日本を代表する大企業がずらりと並ぶ産業都市でもある。その顔ぶれは京セラ、村田製作所、任天堂、オムロン、島津製作所、日本電産、ワコールなど、一度は耳にしたことのある企業ばかりだ。
これらの大企業は日本の高度経済成長とともに発展を遂げてきた。しかし、当然ながら最初はよちよち歩きのスタートアップに過ぎなかった。すなわち京都には、粘り強く企業を育てる風土がある。そのため、昔から「ベンチャーの都」とも呼ばれている。
京都知恵産業創造の森は、2018年11月に設立された一般社団法人である。産官学金で構成された京都スタートアップ・エコシステム推進協議会の事務局を担い、スタートアップ支援にも励んでいる。同法人でスタートアップ推進部 次長を務める川口高司氏は、「それまで一元化されていなかったスタートアップの情報や課題を集約・可視化し、エコシステムを形成するのが狙い」と語る。

川口氏によれば、京都のスタートアップの特徴は「ライフサイエンスとハードウエア」だという。ライフサイエンスは京都大学をはじめとする、大学や研究機関の高い基礎研究・技術力がもとになっている。ハードウエアの発達は、上記で述べたような、先達のモノづくり企業が成長したエコシステムによるもの。実装に向けたプロトタイプを作りやすい環境が整っている。最近では、工場の最適化に資するデジタルツインに挑むスタートアップも出てきた。
圧倒的な学生の多さも起業文化を後押しする。京都市は人口の約1割を大学生が占め、あちこちに若いアイデアがあふれている。「東京から見ると洗練されていない印象もあるが、思考は独創的なものが多い。また、長い目で企業を育てる文化があり、ゆっくりと物事に取り組める街だと考えている」(川口氏)。
川口氏は京都市職員との兼任だが、京都知恵産業創造の森の設立前から公的な立場でスタートアップ支援に励んできた。京都市が補助金を提供した1つであるBIOME(バイオーム)は、同名の生物コレクションアプリが大ヒットした京大発スタートアップ。「バイオームは、ゲーミフィケーションを通じて生物多様性の保全を目指す企業。創業した2017年はSDGsへの関心がいまほど高くなかったが、この2年ほどで急激に脚光を浴びた。次世代のスタートアップが着々と京都から飛び立っている実感がある」(川口氏)。
そのほかにも、2010年代には再生医療製品を手がけるiHeart Japan、半導体の新規材料開発に取り組むFLOSFIA、核融合の実用化に挑む京都フュージョニアリング、AIスタートアップのHACARSなど、高度な技術力に裏打ちされた注目企業が続々と誕生した。川口氏は、「それらのディープテックはすでに実装され始めているが、本格的に社会に実装されるのは恐らく5年〜10先の話。2010年代にまいた種が、これから花開くのが待ち遠しい」と期待する。

2021年には、京都スタートアップエコシステム推進協議会メンバーの「京都産業21」が旗振り役となり、京都知恵産業創造の森も後援する「エンジェルコミュニティ」が発足した。京都のモノづくり企業経営者、および京都にゆかりのあるエンジェル投資家から成る組織で、シード/アーリー期のディープテックスタートアップを発掘・支援するのが目的だ。アドバイザーにはトーセ、島津製作所、堀場製作所、SCREENホールディングス、村田機械などのトップ層が参加。孫泰蔵氏もエンジェル投資家として名を連ねている。
「発掘に向けたピッチをこれまでに3回実施されたが、彼らからの出資までは至っていない。それだけ経営層の見る目が厳しいということ。なぜなら、彼ら自身が道を切り開いてきた先駆者たちだからだ。ただし、支援までのハードルは高いが、一度支援したら長く付き合うのが京都の特性。磨き上げた先に大企業との協業の可能性が十分にある」(川口氏)
こうした街ぐるみの個性を、川口氏は「4C」という言葉で表現する。「Compact、Contents、Comfortable、Comparatively Cheap(比較的安い)。東京のスタートアップが京都に支店を置くケースが増えているのは、そこに魅力を感じているからではないか。もちろん、京都という街のブランド力もあるだろう」と川口氏は分析した。

自らが京都出身であるNDVの加納氏は「一見、京都のスタートアップは技術オリエンテッドのようにも思えるが、きちんとビジネスにも目が向いている。5年先のサービスの種を探そうとすると、京都のスタートアップにヒントをもらうことが多い」と語る。2021年4月には京都知恵産業創造の森とNDVによる共同イベントを開催するなど、両者は今後も関係を強化していく予定だ。ベンチャーの都、その系譜を受け継ぐための後方支援は続く。